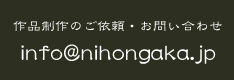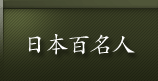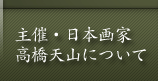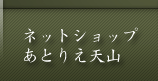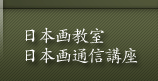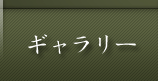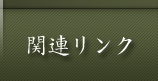さ〜た行の日本の名画家
さ行の名人
酒井抱一(さかいほういつ) ↑ページのトップへ戻る
宝暦11年7月1日(1761年8月1日) - 文政11年11月29日(1829年1月4日

三河侍と言えば、質実剛健を絵に描いたような武士団。
家康の天下統一の大黒柱となったことはつとに知られている事です。
さらに、三河以来の譜代大名と言えば、本多氏、酒井氏、阿部氏、などなど、
幾多の家臣群を形成し、幕末まで続いた家系もありました。
たいていの場合、初代はまだ逆境にあった家康に仕え、
苦楽を共にしてきた筋金入りのツワモノ達ですが、
二代目、三代目と代が変わるごとに、よく言えば洗練され、
悪くすると軟弱化していった事もまた、歴史の事実でありましょう。
お互いの権力抗争に地道をあげる事も少なくはありませんでした。
中でも酒井家は、明治時代に入っても、華族として遇されるほどに、
無視できない大勢力を維持し続けてきたのです。
ざっと辿れば、長男の系列の左衛門尉家(さえもんのじょうけ)、
次男の系列の 雅楽頭家(うたのかみけ)とに分かれます。
江戸時代後期の絵師、酒井抱一、本名、忠因(ただなお)は、
紛れもなく、正当の酒井雅楽頭系、を受け継ぐ姫路城城主、であり、
勿論姫路藩主であった酒井忠仰の次男坊としてこの世に生を受けたのでした。
当時は大大名の嫡子ともなれば、当然江戸屋敷で生まれ、江戸で育つのが当たり前でしたから、
兄忠以(ただざね)が、後を継いで、藩主となってからも、
弟君は、江戸屋敷で好きなことをしていればよかったわけです。
そのことが幸いして、この稀有な天才は、思う存分才能を開花させることが出来ました。
それは、それは、ヨダレものの境遇にいた人なのです。
現代の世知辛い世相の中で日本の伝統芸術を培ってゆこうと涙ぐましい苦労を重ねている私などからすれば、
全くウラヤマシイばかり、ホント! コノヤロウ!ってなもんです。
酒井雅楽頭系は、始め 武蔵国川越藩1万石→上野国前橋藩3万3千石(後、最大時15万2千石)
→播磨国姫路藩15万石 と転封されてゆく度に膨れ上がり
今でも世界に誇る日本城郭建築の最高峰。
白鷺城と称賛される姫路城の所有者となるのですから、
その嫡子の権勢たるや、次男と言えどもいや、嫡男の責任がない分だけ
芸術家としては、好都合だったということになります。
酒井家が最高に繁栄を謳歌している時代に、嫡子の次男として生まれた超ラッキーボーイであったのです。
この、どうしょうもない??道楽息子?が金と地位に任せてやったことは数知れず、
手始めに、17歳で元服。1,000石を与えられてから、
画業は初め狩野高信(かのうたかのぶ)から狩野風を学び、
また宋紫石(そうしせき)について沈南蘋(しんなんぴん)の写生画風、
歌川豊春(とよはる)から浮世絵、
さらに土佐派、円山派などの技法を習得、
親交あった谷文晁(ぶんちょう)からも影響を受けるなど、やりたい放題。
さらに画(え)はもちろん、俳諧(はいかい)、、和歌、連歌、国学、書、
さらに能、仕舞などの諸芸をたしなみ、手を出さない分野はないほどに
あらゆる日本伝統文化を堪能。文字どうり、才能に任せて遊びまくっていました。
その挙句37歳で出家を志し、
京都西本願寺の文如上人(ぶんにょしょうにん)のもとに剃髪しましたが、
わずか十数日の滞在で江戸に戻り、翌年浅草千束(せんぞく)の庵(いおり)に移って閑居。
贅沢三昧に過ごし、住む所などドウにでもなる立場にありながら、
あえて、庵で閑居!!!!
全く、我がまま放題です。
抱一と言う号はこのころを契機に用いられる様になりました。
出家した後は尾形光琳に私淑。
光琳の事績の研究や顕彰に努め、彼の没後100年に当たる文化12年(1815年)
百回忌記念の光琳展覧会を開催(その時の縮小版展覧図録である『光琳百図』上下は、
当時の琳派を考える上での基本資料となり、さらにこの図録は後にヨーロッパに渡り、
ジャポニスムに影響を与えた)、のでした。
“この展覧会を通じて出会った光琳の優品は、抱一を絵師として大きく成長させ、
琳派の装飾的な画風を受け継ぎつつ、円山四条派や土佐派、南蘋派や伊藤若冲などの技法も
積極的に取り入れた独自の洒脱で叙情的な作風を確立し、いわゆる江戸琳派(えどりんぱ)の創始者となった。”
と、ウィキペディアでは言われています。が、
江戸琳派というのは、江戸狩野に対する学問的表現。
本人にしてみれば、ただ心の赴くままに、やりたい放題しまくっただけ。でありましょう。
絵師とは言え、大大名の御曹司であったことをフルに活かして、
わが身の才をも肥やしていったわけで、本物は本物を知る。
没後100年を経た光琳に光を当てたのは、まさに、慧眼。
誠に要を得た画業であると思わざるを得ません。
道楽もここまでやれば人類愛!
決して、ただの馬鹿殿様ではなかったのです。
写真術の後塵を拝していたヨーロッパ芸術界に脅威の革命をもたらすことになった
直接のきっかけ、“琳派”を完成させたのはコノ天才でありました。
光悦、宗達、光琳、もつまるところ、コノ殿様の集大成を待たなくてはならなかったのです。
「夏秋草図屏風」の通称でも広く知られる代表作の銀屏風 「風雨草花図」は、
一橋徳川家がかつて所持していたもので、彼の最高傑作とされています。
俵屋宗達の名作に影響を受けた光琳の金屏風「風神雷神図」(重要文化財)の裏面に描かれたもので、
現在は保存上の観点から「風神雷神図」とは別々に表装されているのですが、
本作は、風神図の裏には風に翻弄される秋草を、雷神図の裏には驟雨に濡れる夏草を描き、
「風神雷神図」と“粋”な照応を示しています。

宗達 風神雷神図

光琳 風神雷神図

抱一 風雨草花図
その他、『十二か月花鳥図』宮内庁三の丸尚蔵館蔵 、
『四季花鳥図屏風』陽明文庫蔵 、など、
御物となり、宮廷貴族系のの所蔵となった名品が多いのは、
王者の風格を備えているからであり
貧乏画家にありがちな生活臭などこれっぽっちもなく、
超然としているかのようだが、そんな臭い気取りすらもなく。
ただただ、品格の高い、ゆくところ可ならざるなき雅の局地は、
大名とはいえ結局万世一系、日本のの御皇室に憧れてのことであり、
とうてい凡人の手の届くような境地ではありません。
三河侍も洗練の極みに立てば遂に抱一となる。 であります。

鈴木春信(すずきはるのぶ) ↑ページのトップへ戻る
1275年 享保10年〜1770年 明和7年


秘すれば花。とは、世阿弥の名言。
浮世絵の大人気をさらに決定付けた、錦絵の創始者、鈴木春信は
美人画の要諦を深く深く会得していた大名人でした。
隠れてよく見えないほうが想像力を掻き立てるのは万国共通。
隠されているからこそ美人に付加価値が生まれるのであって、
その美しさをさらけ出してしまっては始まりません。
なるべく隠す、隠しに隠した上でちょっとだけこぼれ出るように見えてしまうのが良い。
絶世の美女とは、そうしたもの。夜目、遠目、傘の内。
昔の人は全く上手く表現したものです。
現代でも美人は三日で飽きる?とか言いますから、、、。
春信描く美人は、蟇目鉤鼻。大して目立つような美人では決してありません。
それにちょっとぎこちないくらいのポーズをとり、
小作りで、手足も長さの割には異様に小さく、肌を露にしている訳でもなく、
殆ど意表をつくような設定があるわけでもなく、
取り立てて派手な格好してるわけでもなく、
特殊なことは一切していないのに、
なぜかとても印象深い美人画ばかりなのです。
この方は、見る人の想像に任せきってしまうことが
美人創作の最大の要件であることを良く知っていました。
国宝源氏物語の作者は、読者の想像を邪魔しないために、
すべての登場人物の顔が、大体同じ。蟇目鉤鼻スタイルを確立させました。
あるいは、日本のことですからもっともっと以前から確立されていたのかもしれませんが。
何せ、紙や絹に描いてある脆弱な絵画なので、
500年もたつと大抵は痛んでしまうために、ずっと以前のことは証拠がなくて、
誰にとっても想像の域を出でなくなってしまうから仕方ありません。
ともかく、春信は、男女を問わず、
美人に対する万人それぞれが持っているイメージを
出来るだけ崩さないことだけに全神経を注いでいます。
例えば、手足が小さい事だけをとっても、
大きいと可愛く見えないし可愛さは美人に直結する大切な共通のイメージだし、
別に現実より小さくても見たいのは現実ではなくて、
美人と言う一つのファンタジーが欲しいので、
立っていられんくらい華奢なほうがきれいに決まっているんだから、
子供ミタイに小さな手だって仕方ない。と言うわけで、
一事が万事それで行くと、春信風、永遠の美女が当然生まれてしまう事となる。
これは、言うのは簡単ですが、誰にも出来る様な業ではないのです。
深い深い人情の機微に敏感な繊細きわまる神経と、
嫌と言うほど、人間関係の縺れでずたずたに引き裂かれても
まだ諦めきれぬ満たされない熱いい思いとを持ち合わせていないと、、、、。
40代での若死にも、想像に過ぎませんが、
ちょっとこの人には滅びの匂いがする。
感情の理不尽さ余って理性のコントロールが利かなかったのでは??
コントロールされ尽くした度外れた創造力は、絵の中だけだった???
この名人の作品のすべてに底流している犯しがたい品位は、
魂の気高さを表しているだけでなく、
決して憧れを捨てない理想の深さをも証明しているに違いないのです。
この名人のおかげで江戸の町民だけにとどまらず、
錦に彩られた夢の実現を垣間見ることの出来たあまたの人々が
どれだけ幸せを感じたか知れません。


雪舟(せっしゅう) ↑ページのトップへ戻る
1420年 応永27年〜1506年 永世3年

国宝指定最多作家であり、日本画の大先祖と言う感じの雪舟は
ちょうど500年前くらいの人。だからそんな昔でもないのに
ずいぶん古代の人のような気がします。
紫式部が1000年前ですからそれに比べれば、、、。
5点の国宝に加えて現存する作品数の多いことでも知られ、
いかに後の人々から大事にされてきたかがわかろうというもの。
それにこの人は政治経済のの中枢にはあまり縁がなく、
山口を中心に中国九州など旅が長かった為に、
作品が分散していた為でもありましょう。
伝、を含めると相当多数の作品が残されているのです。
86年の長い生涯で、48歳の時に庇護を受けていた
大内家のおかげで渡明の機会に恵まれました。
遅咲きと言ってよく、明へ渡る前のことはあまり良く分かっていません。
が、元は拙宗と名乗っていた可能性があって、その説に従えば、
明に渡る前に描いた絵も残されていて、そうでないとする説の人に言わせると、
明から来た渡来僧であるとも言われていますが、
確かに別人と思われるくらいグレードアップしたのです。渡明を境にして。
吉備の生まれ、幼少のころ頃おいたをして叱られ、
納戸に縛られて押し込められた時、涙で描いたネズミが歩いて逃げたとか??
京都東福寺に入り禅僧としての修行を相国寺でつみ、
物心ついてからずっと黒衣の禅僧のまま。
大内の殿様に才を見込まれての渡明でしたから、
言うなれば画家としての修行は大してしないままに
才だけで絵を描いていて、そこそこ認められてはいたが、明に渡って初めて
本格的な絵画の勉強をすることになる転機となったのが、
48歳だったと言うことではないかと思われます。
何れにせよ大器晩成に違いありません。
明では模写しまくって来たようで、その作品も保存されていて、
それがあまり上手くないので。どうやら時間がなかったか、
あるいは正確にやるのが面倒だったか?大体を写し取っておしまい。
しかし用筆や墨のこと等、得るところは大であったのでしょう、
これ以後作風が固まり、雪舟様と言う風格が、めきめき現れて出てきます。
とにかくこの人の絵は、色彩がない、着彩画も在るにはあるが、
わずかな色味であり、藍や黄土、ベンガラなど、手軽で安価な絵の具ばかり、
めったに絵の具らしい絵の具を使わないのです。
比類のない多彩さから言っても水墨画だからと言う理由だけでは
かたずけられません。田舎の地方作家、だった為に、
高価な絵の具は手に入れることが出来なかったと言うのが本当のところでしょう。
名人雪舟が??まさか!!と思われるかもしれませんが、
当時の絵の具は超高級品。わずかに高価な絵の具はあっても、
すべて中央の宮廷画家のための品。田舎の禅坊主の出る幕はありませんでした。
しかし、それが幸いしたのです。
思うようには絵の具が手に入らない、表現したいものはたくさんある、
紙と墨だけで、思う存分表現したい。どうしたら?
その為の特別な手段を明にまで渡って獲得する。と言う遠回りが、
却ってこの天才の真価を引き出したのです。
特別な手段。これは写実を基本にして、抽象することでリアリティを得る、
という全く新しい解釈を絵画に取り入れることでした。
人、建物、木、岩、、、水波、山岳、、、。
あらゆるものを感覚としてとらえ、明で学んだ筆法を利用して、
様式化と言う抽象化をすると、墨だけで描いたほうが、
却って臨場感が出ることを彼は発見したのです。
彼を取り囲む環境がこの大発明を生む嫌もオウもないきっかけになったのでした。
画家に絵の具を渡さない。と言う逆境。
それ故に墨だけで誰にも到達できない境地にまで達した。
国宝天橋立図を見てください。
この絵をどこから描いたか?と言うことが、今でも話題になっているくらいですが、
天橋立がこんな風に見える位置など現実にはありません。
なぜってこれは雪舟の頭の中で組み立てられ、抽象された天橋立だからです。
おおよその地形、あちこちからの数枚のスケッチ、それらを元に絵画として美しく、
しかも名所図解としても分かりやすい、両者を兼ね備えた創意を工夫して
抽象化した上出来上がったのがこの名品。
雪舟の真骨頂はここにある。ピカソより先んずること500年。
世界の近代史はこの方によってその扉を開けた。
と言うのも決して言いすぎではありません。そして、
45センチ×29センチの小さな画面の2枚を対にして、
地球の空気すべてを描ききったような壮大な山水画が、
教科書でおなじみの国宝「秋冬山水図」です。

秋景山水図

冬景山水図

天橋立図

山水長巻 部分

山水長巻 部分
た行の名人
高階隆兼(たかしなたかかね) ↑ページのトップへ戻る
生没年未詳。鎌倉後期


延慶2(1309)年から元徳2(1330)年までの記録がたどれ、
生没年など、分かっていない事の方が多いのですが、
このあたりが円熟期だったとすると、
北条氏が滅んだ頃には少なくとも初老を迎えていたことでしょう。
鎌倉幕府がなくなるという激動の時代。
宮廷絵所預(えどころあずかり)で、
右近将監(うこんしょうげん)という位まで得ています。
文化庁長官と言うところでしょうか、
ニュアンスはちょっと違いますが、かなりの高官と言えます。
この名人は特別の存在。名人の中の名人。と言うのも通史上、
日本画の基準作品と言われているほどの名作を残しているからです。
春日権現霊験記絵がそれ。20巻に及ぶ超大作画が
この名人の作品であることは間違いなく、
おそらくその高さにおいてその深さにおいて
この絵を上回るものがあるのかどうか
ちょっと思いつかないくらいの傑作です。
源氏物語絵巻も確かに素晴らしい傑作に違いないのですが
断片的に残されているだけで、やつれも甚だしく、
規模から行ったら春日権現記に比すベくもありません。
大観の生成流転、この絵巻も超名作と思いますが、
これにかなうかどうか???さすがの大観先生もちょっと脱帽かもしれません。
ひとつ京都博物館あたりでこの2点を並べてみると
ちょっと面白いことになるかと思われます。
現在この絵巻物は、御物となり、三の丸尚蔵館の管理下で、
この度の今上陛下御在位20周年を記念して一巻ずつ丁寧に修復され、
すっかりきれいになりました。奈良春日大社の縁起をテーマにして、
春日明神の影向図(ようごうず)や、神鹿たち、社殿建築の大工仕事、
人々の暮らし、寝殿造りの庭園美、四季の風景、紅葉に新雪、
飛び立つかもの群れ、明恵上人、馬上の武者、などなど。
あらゆる文物が春日大社と共に表現されているので、
資料的価値まで備わっている、トンでもないシロモノなのです。
線の行くとして可ナラザルなきほどの流麗さ、
色彩の堅固で同時に深くやわらかい繊細さ、格調高い、と言う言葉は
この作品のためにあると言っても過言ではありません。
鹿が沢山登場するのですが、
現画壇で指折りの動物画家も舌を巻くほどの鮮やかさ、
この生命感は到底表現しきれないレベルだそうです。
さりげない線の表現の中に、奥の深い精神性さえ感じさせ、
簡単に模写することさえ難しいと、解説してくれました。
後鳥羽上皇が鎌倉の幕府に立ち向かい逆に隠岐へ島流しにされて以来、
天皇家の幕府に対する屈従は続いていました。
幕府ばかりでなく藤原氏の専横をも横目で見ていなくてはなりません。
北家を筆頭とする藤原家は陰に陽に天皇家を輔弼すると見せながら
実権を握りたがり、かなり横暴なことも続けてきていたのです。
その権威の寄ってくるところが春日明神でした。
大先祖鎌足もルーツを探れば、天照大御神に下された
天孫二二ギノ命の降臨に付き従ったアメノコヤネノ命の後裔。
つまり本元は天津神であったと言うプライドが、一族を貫いてきたのです。
その事を実証するためにこの様な絵巻物を描かせる必要があったのでしょう。
時の権力者は時の名人にその役を与えたのでした。
高階家は藤原家と繋がっていたかもしれませんが、
隆兼は、その望みをかなえるに余りある力量を持っていました。
後に藤原家筆頭となる近衛家は、江戸時代に入ると
天才画家・渡辺始興にこの絵巻物を正確に模写させ、
オリジナルが朽ちることを予測したように先手を打っています。
陰に陽に権力の維持に相当の神経を使って来たのは藤原氏の伝統なのです。
しかし時の名人渡辺始興の手をもってしても
この高階隆兼の画格には遠く及ばなかったのでした。
なぜ一般には高階隆兼のタの字も知られていないのか、
全く不可解であり不愉快でもありますが、
人類の叡智の極とも言うべき文化の塊について
あまりにも無関心な人間が多すぎるのでしょう。
ことに現代は洋物を基準に物事を決め付けているので、
相当な力量ある人物であってさえ、根本を履き違えているのを見ると
価値観の相違はなんともいた仕方がない、とがっかりする事甚だしいのです。
日本画の絵の具の白は大抵は胡粉で表現するのですが、
この絵巻物にはジンクホワイト、
鉛白(えんぱく)が使われていることがわかっています、
片ぼかしと言う一種の遠近法をわざと使わないことや、
これ以上ない繊細さの線描など、技法的にも各所に工夫がなされ、
加えて絵の具の優良さは、驚くほど、修復で蘇ったことも手伝って、それは鮮やか。
繰り返し繰り返し褒めちぎってもまだ足りないくらいの超超超大作!
この名人に、天皇家の権威のための絵巻を描かせたら、
いったいどんな名作を生み出したことか、想像するだにわくわくしますが、、、、?
それはこれから、彼に代わって私がやるべきものと確信しています。
俵屋宗達(たわらやそうたつ) ↑ページのトップへ戻る
生没年不詳 - 慶長から寛永年間に活動
江戸初期の慶長年間から寛永と言うと、西暦で言えば1600年から1640年、
活躍期がこれとすれば産まれたのは遅くとも1580年。ですが、慶長7年
(1602年)5月に福島正則の命令で行われた平家納経の修復に関わり、
その内3巻の表紙と見返しの計6図を描いたと見られると言うのが、
史料上確認出来る宗達の事績の初見とか。これを信じるとすれば、
厳島の平家納経は、かの平清盛の発願で生まれた、国宝中の国宝。
二十歳そこそこの若者にいじらせるはずは無く、
このとき宗達は既に名声を勝ち得ていなければならない筈で、
少なくとも50歳くらいにはなっていたかもしれません。
かの光悦が、1558年生まれですから、
もしも光悦と宗達とが同い年であったら、平家納経の修復は、
44歳の時と言う事になります。光悦の項で述べましたが、
この宗達と光悦とはまるで欠点を補うかのような関係で,
生涯を共にしていたのです。年も殆ど同じだったに違いない。
不世出の大天才光悦の唯一つの欠点?は、絵を一枚も残していない事。
ホントに一枚もない。ソレをあたかもフォローするかのように、宗達は、
大和絵から、土佐派から、狩野、浮世絵、ともかくソレまでの
あらゆる流派をひっくるめて、学び取り、
それらのエッセンスだけを抽出して
鮮やかに、軽々と、まるで、冗談かなにかのように易々、
数多の名作を作り終えています。
そうとしか思えないくらいに彼の画業は間口が広くしかも深い。
単純化するに何の躊躇もない画風は、世界史始まって以来の、
元祖アバンギャルド!! といってもいいくらいです。
あのエネルギーが有り余って、無駄に力が入りっぱなしの画業人生
だったピカソも、宗達をもっと研究すれば、ずーっと楽に,
一桁も二桁もグレードアップした、良い絵を残せただろうに。
と残念に思うくらい、この人は粋。洒脱。
ホントに光悦の垢抜け方とそっくり。まるで血を分けた兄弟のよう。
洗練のされ方が実に良く似ているんです。
私はどうしても光悦の大天才が絵を描かなかったとは思えない。
宗達を見ると光悦が宗達を名乗って、絵を描いていたとしか思えないのです。
ちょっと考えても現在でも、国宝中の国宝と言われている平家納経を、
易々と誰にでも直させるはずはありません。
近代にも安田靫彦に依頼して、平家納経の修復がなされた事があります。
時代は違えど安田先生がこの仕事を依頼されたのは、功成り名遂げた、晩年の事。
修復と言っても古びたお経にある絵を古びた様にではなく、全く新しく、
汚損した部分だけ、新しくすると言うものでした。
なぜって、、、宗達の直したところを真似たから。
つまり、修復という作業には大きく二種類あって、
現状を大切にする、修復と、完成当時はこのようであったろうという
再現修復とがある。前者は、修復専門家の仕事であり、
後者は作家の仕事である場合が殆どです。
つまり宗達も安田先生もこの方以上の再現修復家は当代にはおりません
と言う、絶対的な周囲の了解が、大前提となっている。
戦国時代の混沌の中でも平家納経は人知れず、保存されてきたのでしょう。
何か不都合があって、どうしても直さねばならなかった。
天下分け目の関が原の直後ですヨ、よほどの理由があったのでしょう。
ソレを依頼出来る絵師は、、、宗達の名声がはっきり定着する前に
そんな仕事を依頼するはずはありません。
光悦なら?誰もが認めたでしょう、あの方ならやっていただける。
あのかたなら誰に異存も無い。
何かの必要で、高貴な方にお見せする場合、
名声も定かでない宗達ではなく光悦が良いに決まってます。
当時の関係者は皆知っていたはず、、???
宗達は光悦の雅号だということを。???
徳岡神泉 (とくおかしんせん) ↑ページのトップへ戻る
明治29年(1896)〜昭和47年(1972) 京都生まれ
京都上京の神泉近くに生まれ、生涯の大半を京都で過ごし、京都で没した生粋の京都人です。
神泉苑は“京都のへそ”と言われ、太古の昔、京都盆地が湖底であった頃の
名残の地下水が泉となって湧き出している処。
“御池”という地名、街路名もこの池により、さらに「司職町」、「式部町」、「主税町」など、
周辺に今でも残る町名から、このあたりが平安京の大内裏に面した官庁街であったことも伺われます。
“風土が芸術を生み出す”、言い古されたこの言葉が、この名人にも当てはまるのですが、
京都のへそに生まれた神泉の画業は京都の原風景に他なりません。
堅実な経済力に支えられた京都中産階級の典型的な暮らし、
周囲の賢明な理解と後援を得てのスタートは順調そのもの。
“東の大観、西の栖鳳、”と並び称された、京都画壇の大御所、竹内栖鳳について学ぶ一方で、
京都市立美術工芸学校に入学、優秀な成績を残します。
続いて京都市立絵画専門学校本科に進み、褒賞、受賞を重ねるのです。
ところが、在学中から許可された文展に挑戦するも落選。次も落選。また落選。・・・・・。
学内ではその実力を大いに認められ将来を嘱望される存在であり続けていたのに、
いざ、世に問うてみれば、挫折の山。と言う状態が以後10年もつづいたのでした。
天才少年と自他共に認められてきた若者にとっては、深刻な打撃。
繊細で自己評価の高い、完全主義。プライドが許すはずはありません。
ずたずたにされた自尊心を引きずって、自意識過剰な行動へと駆り立てられるのでした。
人目を避け、孤独を求める逃避行が始まります。
遂には京都を出奔し、放浪することに。
まさに青春の彷徨。折れてしまいそうな心を、捨てることは出来ない絵を描くことで支える日々。
この大正8年頃から大正12年まで続く京都出奔事件を、解決してくれたのは富士山でした。
富士山麓に移り、富士を仰ぐ暮らしを始めて、深刻な挫折の原因である捨てきれない絵に又、
正面から向き合えるようになるのでした。生涯の伴侶も見つかり、
答えが出るのはまだまだ先のことですが、どうやら目の前の壁と対峙する気持ちは定まったようです。
このころに神泉を名乗る様になります。
生涯京都を離れなかったこの人が唯一離れたこの時期に
皮肉にも京都のへそ、の名を名乗るようになるのです。
そして大正12年の関東大震災をきっかけに、院展の近藤浩一郎の勧めもあって、
妻子を連れ、京都へ戻ることに。名人神泉誕生と言うところでしょうか。
福田平八郎など、当時の京都画家との交流や、東洋画の研究、超写実的手法,
絵にならない題材の絵画化、などなど勉強を重ねながら遂に、帝展初入選。そして特選。
神泉、としての歩みはなかなかのものでありました。
が、またまた壁が彼の行く手をはばみます。
今度は、“入選、特選、と、「絵らしい絵」を描くようになってしまった自分に不満”
で、絵がかけなくなる・・・・・。
この天才の目指すところは非常に高いものでした。
それ故にスランプも長く深刻で、立ちはだかる壁は常に大きかったのだと思われます。
しかし、神泉はそれを見事に跳ね除け、この人でなければあらわせない、
そう簡単には届かない境地を獲得してゆくのです。
“わたくしたちの先輩は、瀧を描いてどうどう、と落ちる瀧の音が聞こえる。
そうした絵を推奨し、そうした精神を良しとした。
これは写実絵画の基にある心のありようのように思える。
わたくしはそれとは違う。もちろん抽象派とはいえないだろうが、
例えば、散る花びらが地に触れる、その瞬間の空間の充実、
ついには、はなびら、でもなければ音でもない、
宇宙の核と相通じるような心境を描きたいのだ。”
“時代が変わり、絵画に装飾性以外の精神的内容といったものが重視されなくなったら、
わたくしは、もう、不用の者となっていいのだと思った。
時代感覚と言うものは好き嫌いを問わず浸透してくるものだ。
若い人たちの形や色に対する感覚の鋭さは驚くほどである。
だからその感覚に生きるというか、時代にいきることは良いことだと思う。
しかし、感覚を超えたところでは、時代に生きることだけがすべてではないと思う。”
“大自然と宇宙のそしてその奥にある核心、摂理、そうういうものを絵の中に追求してゆきたい。
この宇宙には、人間の力では遠く及ばない偉大なものがある、
自分はこれに向かって少しでも近づこうと、死ぬまで努力しなければならない、
それは止むに止まれない心の要求なのだ。”
神泉自身が、このように言いきっているのです。
<極度の単純化により、把握した宇宙観を画面に象徴する>。
彼の後半生は、初手から高い評価がありましたが、いよいよ煩雑な自然主義を捨てて、
思い切った単純化を断行し、そこに独自の余白美を構成して、人々の感動を集めるようになって行きました。
昭和40年日展出品のために描いた“富士山”。
東京の会場に搬入したにもかかわらず迷った挙句出品を取りやめ、持って帰り以後、
公表することなく死後初めて公開されたこの“富士山”こそが、この 名人の傑作でありましょう。

流れ

緋鯉

鯉

赤松

赤松

仔鹿

苅田

富士山
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ページのトップへ戻る
ページのトップへ戻る